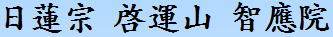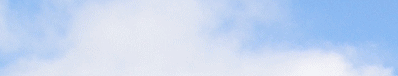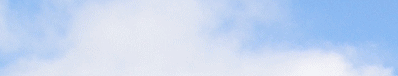●長者窮子(ちょうじゃぐうじ)の喩え
妙法蓮華経信解品第四に説かれる長者窮子の喩えです。
幼い時に父からはぐれて他国を放浪して何十年になった人がいました。年とともに貧乏になり、衣食を求めて各地をさまよい歩き、たまたま故郷にやって来まし
た。父は子供を探し出せなかったけれども、社会的には成功して大富豪・長者となり、町にお城のような立派な邸宅を構えていました。その倉庫には宝が満ちあ
ふれ、大勢の使用人が使われていました。父は片時も子供のことが忘れられずいつもこう考えていました。「自分はもう年老いた。もし万一のことがあればこの
財産は失われてしまう。もし子供を探し出して財産をすっかり渡すことが出来たならば、どんなに幸せであろうか。」
ところが、さまよい歩いていた子供は偶然にも父の家の門前に立たのです。何も知らない彼は、こわごわと中をのぞくと、多くの従者にかしずかれて美しく身を
飾り、あたりを圧倒する威厳を具えて命令を下している主人の姿が見えました。子供は恐怖を感じ「これは王様に違いない。私とは別種類の人だ。ぐずぐずして
いて捕らえられては大変だ」と思い、その場から逃げ去ろうとしました。
ところが父は夢にも子供のことを忘れませんでしたので、ただちにこれはわが子だと見破り、側近に命じて追いかけて連れもどそうとしました。子供は驚愕し「私は何も悪いことをしていません。何でつかまえるのですか」と大声でわめき、恐ろしさのあまり卒倒していました。
このありさまを見て父は「水を掛けて目をさまさせよう」と命じ改めて子供を教育することを考えました。それは子供が自らをいやしいものと思いこみ、心構え
がいやしくなっているために、高貴な者を恐れるのだと知って、はじめから父親と名のらず、方便によってだんだんと誘導して、最後には本当の生まれを明らか
にしてやろうと考えたのです。そこで使いをやって「許してやるから好きなところに行きなさい」と伝えると子供は喜んで貧しい里へ行き、そこで仕事を求めま
した。
ほどなく父は、みすぼらしいなりをさせた二人の家僕を子供の所へ差し向け、次のようにいわせました。「良い仕事がある。賃金が倍も貰えるよ。便所(糞)掃除だが、わしらと一緒に働かないか。」子供は快くやとわれて忠実に働きました。
長者の父は子供をあわれと思い、ある時、今まで着ていた上等な服を脱ぎ捨てて、きたならしい服に着替え、便所掃除の道具を持って、おどおどした様子で子供
に近づいて行きました。そして共に働いている人をはげましたりして子供を安心させます。こうして回を重ね子供とすっかり親しくなってから次のように申しま
した。「お前はここで働いているがよい。余所へ行ってはいけない。家にあるものは何でも遠慮なく使いなさい。私のことを実の父親のように思いなさい。私は
年取ったがお前はまだ若い。今後お前にはとくに目をかけてわが子にようにしよう。」と。そしてすぐに名前をつけてやりました。子供は大変に喜びましたが、
まだ自分のことを余所から来て働いているいやしい人間と思っています。しかし、こうして二十年もたちましたので、心はすっかりうちとけて邸へ出入りも自由
になりましたが、本心はまだはじめの頃の心と変わっていません。
そのうち父は病気となり死期が近づいたのを知ったので、子供に財産をつがせようと思い「私とお前はもう心が一つになっている。財産を失わないようにしなさ
い」といって、一切の管理を子供にまかせました。子供は非常に喜びましたが、少しの財産も所有しようとする気を起こしませんでした。自分はいやしいものだ
という気持ちをまだ捨てることが出来なかったのです。そうしているうちに子供の心は向上して大きな心構え(大志)を持つよういなりました。いよいよ臨終の
ときに、長者である父は、枕もとに、親族・国王・大臣はじめ多くの身分の高い人々を集めて宣言しました。「ここにいるのは私の実子です。今後は我が家の財
産の一切はこの者の所有である。」そして今までのいきさつを詳しく話して聞かせたのです。子供は父の言葉を聞いて大いに喜び「私は求める気持ちが少しもあ
りませんでしたのに、この宝蔵が自然に手に入りました」と語ったのでした。
このたとえ話は、声聞・縁覚を長者の子でありながら幼児に流浪して自己の身分を知らず卑賤であると信じている者に喩え、仏を父の長者に喩えています。長者
は見つけてあらゆる手段を用いて次第に嗣子たることを自覚させたのです。そのように仏は自ら声聞・縁覚と思っている者に種々の方便を設けて菩薩としての自
覚を持たせるということをを喩えたものです。
参考資料
『法華経講義 上』
『日蓮辞典』
『法華経大講座』
他