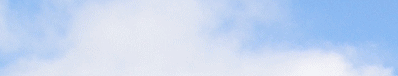●三草二木(さんそうにもく)の喩え
妙法蓮華経薬草喩品第五に説かれる三草二木の喩えです。
たとえば、この全世界の山・川・谷等の地に生い茂っている灌木(かんぼく;丈が低く、根もとから幹の群がり出ている木。ツツジ・ナンテンなど)・ 喬木
(きょうぼく;幹が堅く、高さ約3㍍以上になる木。松・杉・檜など。)もろもろの薬草、大中小の木や林などは種類がいろいろあって名も形も異なっている。そこへ空一杯に雲が拡がって雨を降らすと、雨は平等に降りそそぐけれども、草や木はそれぞれの大きさに応じて水を吸い枝葉を茂らせ花を開く。これら草木は一つの地面に生え、一つの雨が潤すところであるが、草木にはそれぞれ差別があるのです。
この譬え話は、仏の人格は大雲が世界をおおうようにあらゆる種類の存在を包容する普遍的なものであることを明らかにしています。また、仏の人格は一雨・一相・一味などの言葉によってたとえられていますが、それは一乗(一仏乗)の思想の展開であるということができましょう。
衆生はさまざまな心構えを持ったものであることを説き示しています。こうした衆生のすべてのものに対して、仏はそれを包容する普遍的な存在として、平等の慈悲をもってひとしく法を説くものであることを明らかにしています。
小の薬草は人天乗、中の薬草は声聞乗と縁覚乗、大の薬草と小樹と大樹は三段階に分けられる菩薩乗をさすものと解釈させています。
乗とは=乗り物。衆生を成仏の彼岸へ運ぶ乗り物。
参考資料
『法華経講義 上』
『日蓮聖人遺文辞典 教学篇』
『角川 漢和中辞典』
『新明解 国語辞典』
他