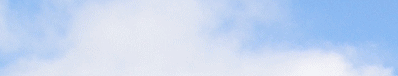●化城宝処(けじょうほうしょ)の喩え
妙法蓮華経化城喩品第七に説かれる化城宝処の喩えです。
非常に珍しい宝物の置いてある場所がありましたが、それは五百由旬も離れた遠い所で、しかもそこへ行くには山あり谷あり砂漠ありで、けわしい困難な道を通って行かなければなりませんでした。人々の内ただ一人の者は、この道の様子をよく知っており、しかも大変な智慧者でしたので、みなのものは彼をリーダー (導師)に選び、その案内にしたがって、隊を組んで宝のある場所をめざして出発しました。しかし道があまりにも険悪なために、途中まで来て、疲れはててしまい「宝物などどうでもよい、やめて引き返そう」などと言い出すものが出てくる始末です。リーダーは「ここでやめては何にもならない。一つ手段(方便)をこうじてみんなを励ましてやろう」と考え、道のりの半ばを過ぎた頃に、神通力によって目の前に立派な城を出現させて見せました。そしてみなのものに向かって「もうおそれる必要はありません、あの城の中に入って休息しなさい。そうすれば元気が回復するでしょう」と告げました。人々は喜んで城の中に入って、一息ついて安らかな気持ちになりました。するとこの様子を見たリーダー(導師)は、この幻の城(化城)を消してしまって、再び人々に告げました。「みなさん、この城は私が仮に作り出したものです。みなさんに休んでもらうためにこうしたのです。宝物のあるところはすぐ近くです。さあ元気を出して出発しようではありませんか。」このように励まされて、一同は助け合って努力し、ついに目的の宝のある場所にたどりつくことができました。
このような喩えを説かれたお釈迦さまは、この喩えの意味を次のように教えられました。
旅行者たち(衆生)が五百由旬さきにある宝処(法華一乗の果)に至ろうとして中途で疲れ止めようとした時、すぐれた指導者(仏)が三百由旬の所に仮に化城(三乗『声聞・縁覚・菩薩』の果)を現して休息させ、その上で遂に宝処に至らしめたという喩え。<br>
五百由旬=一由旬は約11.2kmであるから五百由旬とは約5600kmである。『日蓮宗辞典』より
参考資料
『法華経講義 上』
『日蓮辞典』
他