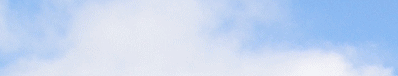●衣裏繋珠(えりけいじゅ)の喩え
妙法蓮華経五百弟子受記品第八に説かれる衣裏繋珠の喩えです。
ある所にお酒好きな男がいました。親友の家に遊びに行ってお酒をご馳走になりましたが、つい飲み過ぎて酔いつぶれ、正体をなくし眠ってしまいました。この
時、親友は外出せねばならない公務があることを思い出し友人を残して家を出ました。かねてより酒ぐせの悪いことを知っていましたので、まさかの時に役に立
つようにと、その男の衣の裏に値段のつけようもない高価な宝珠・宝の珠を縫いつけて置きました。男は酔いつぶれていましたので、そのことに気が付きません
でした。やがて目をさまし、酒に酔って定まらない目付きで起き上がり、そのままふらふらと他国に流浪の旅に出て行ってしまいました。生来怠け者でしたので、ちゃんとした職を得て働くことが出来ず、わずかの賃金を貰って、その日暮らしが出来ればよいという程度で満足していました。
ところが、ある日、街をさまよっている時、かつて宝珠を縫いつけてくれた親友にばったり出会ったのです。親友はみすぼらしい友の姿を見ていいました。「何
と愚かな人間だろう。ただ衣食を求め歩いてこの体たらくとは何ごとか。私は昔、お前さんがもっと楽な生活が出来るようにと思って、高価な宝珠を衣の裏に縫
いつけて置いたが、あれはどうしたのか。たしかにあるはずだ。それを利用しないで、ただ苦労して自活の方法を求めているのは愚かなことだ。あの宝珠を元手
にして商売をしなさい、そうすれば貧乏することはないのだよ。 」
このようにいわれて、男は初めて宝珠のあることに気がつき、自分はもっと金持ちだということを自覚したのでした。
この物語の宝珠とは、物質的な価値というのではなく、精神的な価値のあるものを譬えているのです。私たちは、だれでも自分には気がつかないけれども、仏の
心と智慧に相当する宝珠を持っているのです。それを「仏性」といいます。仏性とは人間が生まれつき持っている仏の性質をいうのです。ただ私たちは自分の仏
性に気づかず、それを開発する努力を怠っているのです。このお酒好きの男は、こういう私たちの凡夫の姿を譬えたものなのです
現在のところはこのように書かせていただいきます。
参考資料
『法華経講義 上』
『日蓮宗事典』