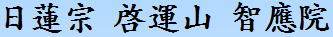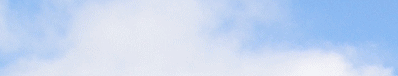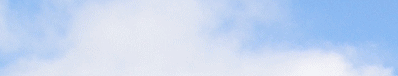●転輪聖王(てんりんじょうおう)
インドにおける理想的な帝王であって、過去に置いて出現したと信じられ、あるいは未来に於いてその出現が期待されるものとして、原始経典以来、仏教聖典の中に広く説かれる。輪を転ずる聖なる王という意味であって、輪とは、政治的統治における権力・権威を象徴する。転輪聖王の観念はインドの諸宗教文献にあらわれるものであるが、仏教聖典に置いて特に詳細に説かれるので、観念には阿育王の事跡が反映しているという見方もある。仏教聖典では一般に、転輪聖王は三十二相を有し七宝を備え種々の特性を具現し、四洲を統一して、正法をもって世を治めるものと説かれている。三十二相は偉人の具える相であって、仏陀が三十二相を具えるとされるのと同じと考え方である。
七宝
輪宝・象宝・馬宝・珠宝・女宝・居士宝・主兵臣宝である。
四洲
仏教の世界観で須弥山の四方にあるとされる、南瞻部(なんせんぶ)洲・東毘提訶(とうびだいか)洲・西牛貨(さいごけ)洲 ・北倶盧(ほっくる)洲である。
阿育王
アショーカ王ともいう。紀元前3世紀頃、インドのマカダ国に君臨したマウリヤ王朝第3代の王。インドを統一、仏教を保護宣布し、第3回仏典結集を行ったという。
三十二相
『大智度論』による。
1,足下安平立相(そくげあんぴょうりゅうそう)
地に立つ時、足下安平にして、地と足が密着して地と足が密着して間に針を入れる隙も無いこと
2,足下二輪相(そくげにりんそう)
足裏に法輪などの相のあること。
3,長指相(ちょうしそう)
指が細く長いこと。
4,足跟広平相(そくげんこうびょうそう)
足のかかとが円満で広平であること。
5,手足指縵網相(しゅそくしまんもうそう)
十指の指間に、鳥の水かきのような金色の膜があること。
6,手足柔軟相(しゅそくにゅうなんそう)
手足が柔軟で色が紅赤であること。
7,足趺高満相(そくふこうまんそう)
足の甲が充満柔軟で、亀の甲のよう盛り上がっていること。
8,伊泥延腨相(いでいえんせんそう)
足のふくらはぎが鹿王のように細く円く微妙であること。伊泥延は鹿の一種。
9,正立手摩膝相(しょうりゅうしゅましっそう)
正しく立った時、両手が膝に摩するがごとくであること。
10,陰蔵相(おんぞうそう)
男根が体内に密蔵されて現じないこと。
11,身広長等相(しんこうじょうとうそう)
身体の縦広左右上下の量が全く等しく円満であること。
12,毛上向相(もうじょうこうそう)
頭から手足にいたる一切の毛の先端がみな上に靡き、右にうずまいて紺青色であること。
13,一一孔一毛相(いちいちくいちもうそう)
身体の一々の孔に必ず一毛を生じ、色は青瑠璃色で、その毛孔より微妙の香気を出うこと。
14,金色相(こんじきそう)
身体、手足などすべて真金色をなし、微妙光潔であること。
15,丈光相(じょうこうそう)
身体を中心に、その四周に一丈の光明を放つこと。
16,細薄皮相(さいはくひそう)
皮膚が細やかで薄く、潤沢を有し、一切の塵垢不浄を留めないこと。
17,七処隆満相(しちしょりゅうまんそう)
両手両足の裏、両肩、うなじの七所の肉がみな隆満端正にして、色が浄らかであること。
18,両腋下隆満相(りょうやくげりゅうまんそう)
両腋の下が充実して虚ならざること。
19,上身如獅子相(じょうしんにょししそう)
上半身に広大で、獅子王のようであること。
20,大直身相(だいじきしんそう)
身体が広大端直にして比べるもののないこと。
21,肩円満相(けんえんまんそう)
両肩が円満豊腴(しゅう)であること。
22,四十歯相(しじゅうしそう)
四十枚の歯はあり、雪のように白いこと。
23,歯斉相(しさいそう)
歯の大きさが等しく、すき間なく密着していること。
24,牙白相(げびゃくそう)
四十枚の歯以外に四牙があって、白く堅く鋭利であること。
25,獅子頬相(ししきょうそう)
獅子王のような広く平らかな頬えおもつこと。
26,味中得上味相(みちゅうとくじょうみそう)
食物はみな最上の味をうること。
27,大舌相(だいぜつそう)
舌が軟薄で広長であって、口から舌を出すに顔のすべてを覆って、額の髪の生え際にいたること。
28,梵声相(ぼんじょうそう)
声が清浄円満で、聞く者をして得益無量ならしめること。
29,真青眼相(しんしょうげんそう)
瞳の色は真青で青蓮華のようであること。
30,牛眼睫相(ぎゅうごんしょうそう)
睫が牛王のように長く整っていて乱れないこと。
31,頂髻相(ちょうけいそう)
頭上に肉が隆起して、髻(もとどり)の形を成していること。
32,白毫相(びゃくごうそう)
眉間に右旋する雪白の白毛があって、そこから光明を放つこと。
『日蓮聖人遺文辞典 歴史篇』
『広辞苑』
他