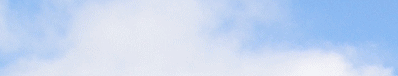●天台大師(てんだいだいし)
538年~597年。智者大師(ちしゃだいし)。智顗(ちぎ)。中国天台宗の実質的開祖。先祖は頴川(中国河南省)の人で,父は梁(南北朝時代の南朝)の官史であったが、梁の554年西魏によって梁朝が滅ぼされるとともに一家は荊州(中国湖北省)に移住した。世の興亡と一家の悲惨な状況の中で出家を志し。梁の555年果願寺の法緒の門に入り、のち慧曠律師(えこうりっし)に師事した。たまたま大蘇山(だいそざん)に滞在していた慧思禅師(えしりっし)に教えを請い、薬王品の一句によって開悟したという。7年の修行の後金陵の瓦官寺(がかんじ)に経論(法華玄義・大智度論・次第禅門)を講じ、法華経の公布に努めた。瓦官寺にあること8年を経て、575年、38歳にして天台山の登ったが、585年、陳の陳叔宝(ちんしゅくほう)の招請によって再び金陵におもむき、587年、光宅寺に於いて『法華文句』を講じ、さらに荊州に玉泉寺を建立して『法華玄義』(602年)と『摩訶止観』(603年)を講じた。前掲三書は天台三大部と称され、智顗教学の中核をなすものである。三大部講述よりさき、智顗は金陵におもむいてまもなくの598年、隋の天下統一が実現し、600年、晋王より「智者」の名を与えられた。
日蓮聖人の教義は、天台三大部をはじめとした智顗の講述書の多大な影響を受けており、『法華経』・『涅槃経』と共にその引用頻度はきわめて多い。日蓮聖人は宗教的主体性とその歴史認識において、自己の思想の系譜を釈尊→天台(智顗)→伝教(最澄)という三国三師に認めている。中でも天台大師智顗については「智顗自身、釈尊の本意たる本門法華経を末法の始めに認め、時機至らざるゆえに、内に秘め、これを末法に譲り、像法相応の経えを述べた」としている。
参考資料
『日蓮辞典』
他