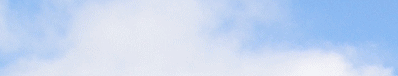●八幡大菩薩(はちまんだいぼさつ)
八幡神に奉った称号。八幡とは、もと八幡=ヤハタ=焼畑を意味し、穀霊的なものの神格化とみられ、九州宇佐の氏神にはじまったとみられるが、奈良時代には託宣神として中央に進出した。やがて八幡神は、応神天皇を主座とした呼称として用いられた。神仏習合の進むなかで、八幡大菩薩の称号が見られるようになる。
奈良時代東大寺の鎮守に勧請されて手向山(たむけやま)八幡となり、平安初期には僧行教により山城男山石清水に勧請されて石清水八幡となり、朝廷の尊崇をうけて天照大神に次ぐ宗廟(そうびょう)神となった。さらに清和源氏の氏神にもなり、のち源頼朝は鎌倉鶴岡に八幡宮を創建され全国に勧請された。
日蓮聖人もまた、八幡大菩薩を天照大神とともに、日本守護の代表的な神とした。更に日蓮聖人は、八幡大菩薩は法華経の会座に列なり、法華経の弘通と法華経の行者守護とを誓ったにもかかわらず仏との約束を果たさないことを叱責した。これは文永8年(1271)の竜口法難に際して有名な事柄である。
参考資料
『日蓮宗事典』
『日蓮聖人遺文辞典 歴史篇』
他